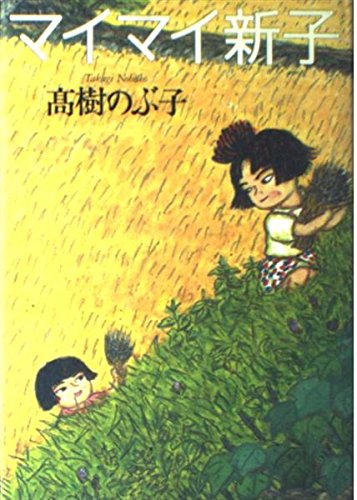※以下は2011年に書いた感想です。
監督:片渕須直、声の出演:福田麻由子、本上まなみ、野田圭一のアニメーション映画『マイマイ新子と千年の魔法』。2009年公開作品。
昭和30年の山口県防府(ほうふ)市。小学生の新子(シンコ)は両親と母方の祖父母、そして妹の光子と暮している。彼女は東京から引っ越してきた貴伊子と仲良くなって、この土地に千年前に住んでいた姫、諾子(なぎこ)のことを空想する。
感想に入る前におことわりしておきたいんですが…。
僕はアニメにかぎらず実写映画でもなんでも基本的には楽しむために観ているんで、けっして上から目線で偉そうに難癖つけて悦に入るつもりはないのです。
たしかに褒めるよりもケナす方が燃えるし楽しいけどさ。…イヤイヤ。
ましてや友だちやそのほかの人たちが好意で薦めてくれたものに文句垂れたりしたくはない。
実際、薦められて観て面白かった映画だっていっぱいあるわけだし。
「好きだ」という人も大勢いる作品をなぜわざわざケナす必要があるのか。自分が「面白くない」と感じたのなら、それは心のなかにとどめておけばいいじゃないか、とも思う。
…でも、それじゃその映画を観たことをほんとに忘れてしまう。
その作品との出会いは「無かったこと」になってしまう。
これまでそうやって忘れ去ってしまった映画がたくさんあるので、不幸な出会いだったかもしれないけど、やはり書き記しておきたいと思うのです。
…って、長々とこんな言い訳してたら、今回観た映画の感想も予想できてしまうではないか^_^;
以下、くわしいストーリー解説、およびネタバレあり。
諾子(なぎこ)とは清少納言の本名、という説がある。
それを担任のひづる先生に教えてもらった新子は、はるか千年前に都からこの地にやってきた少女、諾子に想いを馳せる。
「魔法」という題名から、どうしても西洋風のファンタジーを連想してしまったのだが、この映画で描かれるのは清少納言が生きていた時代の周防国(すおうのくに)である。
というと、では主人公が千年の時を越えて平安時代のお姫さまに出会う映画なんだろうか、と思ったりするけど、実は映画の大半は昭和30年の新子の日常描写に費やされる。
ちょうどアニメ版『ALWAYS 三丁目の夕日』といった趣き。
新子は髪の生え際につむじ(マイマイ)があって、そのためにそこの部分の前髪がいつも突っ立った刈り上げ頭のおてんば少女だが、空想好きでもあって、都会っ子で引っ込み思案の転校生、貴伊子ともすぐに打ち解ける。
このあたりの描写は丁寧で好感がもてる。
おなじく刈り上げ頭の妹、光子が可愛い。
三〜四歳ぐらいの光子はちょうど昭和24年生まれの僕の母と同世代なので、自分の親が幼かった当時の風景を見る興味深さや感慨はあった。
三人でウイスキーボンボンを食べて酔っ払う未成年の飲酒描写もあり。
また、おてんば新子は同級生や上級生の男の子たちとも仲が良く、いっしょに溜め池を作る。
汗をかいて服を泥んこにしながら遊ぶ新子たちの姿には懐かしさを感じる。
もっとも、アニメーションで自然のなかで遊ぶ喜びを追体験する、ということに対しては、若干疑問もある。
この映画には目に見える形での非現実的な「魔法」の描写はないので、たとえば新子たちが自然や農家の畑のなかで小トトロを見つける、みたいな展開はない。
昭和30年の場面では、基本的には写実的な描写がつづく。
それはたしかに郷愁を誘うし、小さな子どもたちには逆に新鮮かもしれない。
ジブリの『コクリコ坂から』(感想はこちら)の感想のなかに「なぜこれをアニメで作らなければならないのかわからない」という疑問が投げかけられているものがあって、作品の存在そのものを否定するつもりは毛頭ないけど、正直僕もちょっとそんな思いはあった。
それに近い感じ。
実写で撮れる題材だし技術的にも可能なのに、資金的に難しいからか、あるいは演出できる監督がいないとか、ちゃんと演技できる俳優がいないなど、理由はさまざまだろうけど、なんとなくとても残念な気持ちになるのだ。
あのね、アニメは実写よりも劣っている、っていってるわけじゃないですよ。
ただ僕はアニメより実写のが「好き」なんで、そう思うだけです。
ここで脱線。
かつて黒澤明が宮崎駿と対談したことがあって、そのとき黒澤監督が「宮崎監督にはぜひ実写を撮っていただきたい」といっていた。
それに対して、後日、宮崎さんは「冗談でおっしゃったんだろうけど、もし本気でいってるなら余計なお世話です」とコメントしてました。
正直だなぁ、宮さん^_^;
アニメーション監督としてのプライドでしょうね。
別にアニメーションは実写の下じゃねーぞ、と。
だから僕だってアニメをバカにしてるわけじゃないですよ。
ある時期までは実写よりもアニメを観ることの方が圧倒的に多かったんだから。
閑話休題。
母親を亡くした貴伊子は若い女性教師のひづる先生に母の面影をみて、その幸せを願う。
これら昭和30年の新子たちの描写と並行して、おそらく新子が、そして彼女と空想を共有した貴伊子が思い描いた平安時代の諾子姫の様子が描かれる。
諾子姫は友だちを欲しがっているのだが、まわりには彼女と同じぐらいの年頃の少女はいない。
退屈した諾子姫が赤い色紙を切って小川に流すと、それは赤い金魚となって千年後の新子や同級生たちの溜め池に現われる。
新子たちは溜め池でひづる先生の名前をつけたその金魚を飼いはじめるが、貴伊子の不注意によって死なせてしまう。
落ち込む貴伊子を元気づけようとして、新子と仲間たちは別の赤い金魚をさがす。
あの金魚は死んでない、きっと生まれ変わったんだ、と。
新子に協力する無口でちょっと暗い5年生のタツヨシは、いつも学帽をかぶっていてどこか『トトロ』(感想はこちら)のカン太や『火垂るの墓』(感想はこちら)の清太を思わせる。
彼の父親は警察官で、道に迷った光子を家まで送り届けてくれたり、居直り強盗を捕まえたこともある「本物の決死隊」。
そのタツヨシの父親が女にだまされてバクチで借金をかさね、自殺してしまう。
…え?
なんだろう、この展開。
警官であるタツヨシの父は、映画の中盤にようやく登場する(その前に遠景で自転車から新子に手を振る場面あり)。
それから10分も経たないうちに死んでしまうのだ。
この作品は原作者の実体験をもとにしているそうだから、この同級生の父親の死も現実にあったことなのかもしれない。
それは別にかまわないんだが、しかしこの超展開はどうなのか。
同じ村に住んでて娘の同級生の父親が死んでるのに、ずいぶんとのどかな新子の母親と祖父母の会話にもこれまた違和感。
「ねぇ、死ぬときって苦しいのかしら」「そねぇな女学生みたいなことを」「長子はそねぇに深刻に受け止めたか」
…って当たり前だろ。人が死んでんの!!バカなのか?
「魔法」とかまったくといっていいほど関係ない話だしなぁ。
それにしても、じいちゃんの声を演じてるの野田圭一さんなんだよなぁ。ロデムや新右衛門さんがおじいちゃん役かぁ…。
金魚をさがして貴伊子を連れまわす新子にタツヨシは「こねぇに貴伊子を引っ張りまわして、自信あるんか。金魚がおらんかったらどねぇする」と問うが、そもそも金魚を死なせたのは貴伊子だし(しかも水のなかに母親の香水を入れるという、小学生にしてもちょっと知恵が足りない行為によって)、このタツヨシが金魚にこだわる理由も、わかったようなわからないような、なんか「もわ〜ん」とした感じで。
それ以前から、この映画を観ていて僕にはずーっと違和感が付きまとっていた。
まず主人公の新子や貴伊子が、小学3年生がちょっと口にするはずもない言葉を発したりする。
「あたし、なんだかひづる先生には幸せになってもらいたいなぁ」
「そういうのも、みんな大人の人たちのおかげかねぇ」
どうしてもそこに大人である「作り手たち」の心情が込められている気がして、ちょっと鼻白んでしまうのだ。
ちびまる子ちゃんが本物の子どもには見えないのにも似て。
たしかに子どもって、大人たちが考えている以上に物事をしっかりと理解していて、時に驚くほど大人びたことを口にすることもあるけれど。
そして、どうしても僕のなかで平安時代の諾子姫の場面と昭和30年の新子たちの場面がしっくり交差しなかった。
諾子姫と宮仕えの貧しい少女の身分や生活環境の違いを越えた交流、それらが新子や貴伊子、そしてタツヨシたちの物語とうまく結びつかない。
なんだかまったく別の話のように見えた。
「パララ~♪」という女性コーラスをはじめエンドクレジット近くに流れる「シング」(カーペンターズの歌が有名)など、劇中で使われてる曲にも違和感(ところどころとても耳に残る素敵な旋律もあったのだが)。
コトリンゴ - こどものせかい
www.youtube.com
とても大切なことを描いているのはわかる(『カラフル』→感想はこちらを観たときにもそれは思った)。
でもなぁ~、って。
それでもとてもよく描かれていると感じたのは、タツヨシが新子とともに街の盛り場にやってきて、タツヨシの父親が死んだ原因を作ったというバーの女のところに乗り込む場面。
子どもたちにとって恐ろしい場所である飲み屋街。そこにたむろする酔っ払った大人たち。
そしてバーの女とその情夫らしきヤクザ。
小学生にしてそんな彼らと対峙するタツヨシと新子の姿には、たしかに胸が熱くなった。
しかもこのバーの女とヤクザは、ただの悪人には描かれない。
けっきょく、タツヨシも新子も彼らをどうにかすることなどできず、ただその胸のうちをぶつけて、帰路につく。
『コクリコ坂』の主人公たちの東京行きの場面は、このように描かれるべきだったと思った。
大人たちは子どもたちには理解しがたい世界に住んでいる。
タツヨシの父親はそんな彼らに殺されて、二度と戻ってはこない。
不条理だ。
しかし、世の中とはそういうものなのだろう。
死んだ金魚が生まれ変わることなどない。
それは新子たちにもわかっている。
それでも、赤い金魚を見たら、死んだあの金魚を思い出すのだ。
小学生ぐらいの子どもって、大人には理解できない、あるいは大人が忘れてしまった感覚で、彼らなりの理由で泣いたり、必死になったりする。
それはわかるんだ。
だから、この映画は巧みなストーリーテリングで観客に夢を見させるというんではなくて、日々のうつろいのなかの喜びや悲しみを散文的に綴った作品なのだ、と理解はした。
大切なのは映画の中身よりも、映画館で、またはDVDで映画を観た、という体験そのもので、それがやがてかけがえのない想い出となる、そのこと自体なんだろう。
映画を観るのは素晴らしい体験なんだ。
だからいろいろ文句つけたけど、こういう流行とは無関係なところで口コミで評判になってさまざまな人たちに感動を与えた作品の存在を、僕は素直に肯定したい。
絵柄はジブリ風、というかかつての東映動画風というか東京ムービー新社風というか、ようするに昔ながらの児童向けアニメっぽいデザインで安心感はある。
ちょっと作画に雑なところがあるが。
たとえば子どもたちの足がズボンやスカートからちょっとありえないような生え方をしてたりするとこ。
多分、宮崎駿なら速攻ダメ出ししてると思うが。
監督の片渕須直さんは、僕はTVアニメ「名探偵ホームズ」や『魔女の宅急便』(感想はこちら)の演出補として記憶していて、また彼は『マイマイ新子』とおなじく単館で小規模に公開された『アリーテ姫』の監督でもある。
『アリーテ姫』は“フェミニズム童話”と呼ばれる児童文学作品が原作。
僕は個人的に創作物におけるジェンダーの問題に関心があるので、この映画も以前から気になっていたが観逃していた。
残念ながら僕の家の近所のレンタル店には置いてないようで。
いつか機会があったら観てみたいです。
『アリーテ姫』(2001) 声の出演:桑島法子 小山剛志 こおろぎさとみ 高山みなみ








![マイマイ新子と千年の魔法 [DVD] マイマイ新子と千年の魔法 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51p5pvtbnzL._SL500_.jpg)